◆◆◆「資本論」の研究◆◆◆
|トップページ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#016:第7篇 資本の蓄積過程(その1)
第7篇 資本の蓄積過程 これまで、商品生産過程を労働過程と見た場合も価値増殖過程として見た場合も、その過程を止めて分析してきました。この第7篇では、これをくり返し行われる連続的な過程としてとらえることにより、本格的には第2部「資本の流通過程」で論じられる資本の運動を、ある程度動的に捉えます。ただし、第2部が資本の運動の量的側面を数式も使って捉えているのに対して、ここでは主に質的側面を捉え、量的な運動についてはその大まかな傾向のみに留めています。
マルクスは論を進める前に、ここでの研究方法、前提条件を厳密に規定します。それは二つあります。まず第一に、商品生産過程が順調に繰り返される前提として、市場で商品が順調に売れて資本が貨幣となり、市場で新たな労働力と生産手段(労働手段と労働対象、機械用具と原材料)を順調に買い入れることができること、つまり資本が流通過程を順調に通過することです。もう一つは、第3部で展開される、剰余価値の利潤、利子、地代への分解を度外視し、資本主義的生産者(第3部でいう「産業資本家」)が他の資本家や土地所有者も代表して剰余価値の全部を手に入れるものと見なすことです。
これは気圧や重力が一定の条件でないと、水は何度で沸騰するかがしっかり観察できない、という条件と似ています。マルクスはていねいに「剰余価値の分割と流通の媒介運動とは、蓄積過程の単純な基本形態をあいまいにする。それゆえ、蓄積過程を純粋に分析するためには、蓄積過程の機構の内部作用をおおい隠すいっさいの現象をしばらく度外視することが必要である。」(④、p969)と説明しています。
真理は単純で美しいさて、マルクスは何でも単純化(何でも価値論に還元)しすぎるとの非難もあります。人間社会はその意識形態のようにそんなに単純ではない、人それぞれだと。でも真理は単純で美しいのです。アインシュタインの相対性理論の基本方程式も E=mc2 と実に単純で美しいではないですか。真理の現れ方である法則も、複雑でもあいまいでもないのです。単純で明確だから、強く作用するのです。いろいろ条件が複雑に組み合わさった法則はあいまいにしか作用しません。マルクスの研究方法は、真理に接近する理にかなったものです。
話しを戻します第21章 単純再生産 は剰余価値が再生産過程に資本として投入されないで、資本家によって全額消費されてしまい、資本の総額と資本の有機的構成(この概念は23章で初めて論じられる)が不変の場合、すなわち、同じ生産過程の単純なくり返し=単純再生産の考察です。序章のようなもので、剰余価値が追加的資本に転化しない場合でも、すなわち資本の蓄積がない場合でもこうなんだよ、と言っているだけで大したことはありません。
強いて言えば、単純再生産のもとでも、「私自身が汗水たらして稼いだお金(本源的蓄積)で始めた事業だ」と威張っている資本家も、しばらくすれば彼のもともとの資本は彼によって消費しつくされ、すべて(前貸しされる労賃さえも)不払労働の体化物=剰余価値で置き換えられ、占められるようになるということ(④、p977)、資本主義的生産過程は(単純再生産であっても)資本主義的生産関係(資本と賃労働)を再生産する(④、p991~992)ということが言いたいのだと思います。
ここでおもしろいのは、労働者の個人的消費は労働力の価値を補填する「生産的消費」(#008:絶対的剰余価値の生産の〔第3編第5章第1節〕参照)か否かの論議です。結論的に言うと、これは理論的な「濫用」(④、p980)です。労働者の個人的消費は、生産過程の外で、労働過程および価値形成過程の外で行われるので「生産的消費」とは言えません。資本にとっては、価値の源泉である抽象的人間労働を維持する最低限の「個人消費」は「生産的消費」であるが、それ以上の消費(労働者の娯楽や奢侈)は不生産的消費だと見えるわけです。(④、p982)(後に資本家の娯楽や奢侈のために個人的サービスを提供する労働者の消費も不生産的消費と批判されます、④、p1008))マルクスの結論は「したがって社会的観点から見れば、労働者階級は直接的な労働過程の外部でも、死んだ労働用具と同じように資本の付属物である。彼らの個人的消費でさえも、ある限界内では、ただ資本の再生産過程の一契機でしかない。」のです。(④、p983)
もっとおもしろいのは、生産的に消費される生産手段と同じように労働者をみなしている資本家が、機械設備と労働者のどちらが重要かを都合によってころころと言い換えると、皮肉たっぷりに資本家とその代弁者の主張を取り上げている部分です。場合によっては資本家も、自分の持ち物である生産手段よりも労働者が重要であることを認めるのです。(「工場主の宣言」、④、p984)
第22章 剰余価値の資本への転化 は資本家が何も費やさないで得られる不払労働=剰余価値を、彼の収入として消費するのではなく、その一部あるいは全部を追加資本として投下する場合、すなわち拡大再生産の場合の蓄積過程を考察しています。あとで出てくることですが、資本の有機的構成だとかの煩雑なことは度外視しています。しかし正確に言うとほんのちょっと先走ってこの暗黙の前提を破っているところが一箇所ありますが、まあ目をつぶりましょう。(④、p999)
第1節ではまずマルクスは例によって資本家個人を登場させシミュレーションを行います。マルクスの例(④、p997)を分かりやすいように表にすると下のようになります。ただし、マルクスは計算に弱いので3回目でやめています。なお、マルクスはこうした拡大再生産のためには、すなわち剰余価値が資本に転化できるのは、剰余生産物がすでに新しい資本の物的構成部分、すなわち追加的生産手段と追加的生活手段を含んでいるからにほかならない、として、第2部で論じる再生産論の「二大生産部門」を予告的に触れています。(④、p996、2~3行)
| 循環 (回) |
投下資本 | 生産物価値 | 追加固定 資本Δc (mの4/5) |
追加可変 資本Δv (mの1/5) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不変資本c | 可変資本v | 不変資本c | 可変資本v | 剰余価値m | |||
| : | : | : | : | : | : | : | : |
| 1 | 8000 | 2000 | 8000 | 2000 | 2000 | 1600 | 400 |
| 2 | 9600 | 2400 | 9600 | 2400 | 2400 | 1920 | 480 |
| 3 | 11520 | 2880 | 11520 | 2880 | 2880 | 2304 | 576 |
| 4 | 13825 | 3456 | 13825 | 3456 | 3456 | 2764.8 | 691.2 |
単純再生産との違いで強調されているのは、ある労働者の不払労働=剰余価値が他の労働者の不払労働を資本家が取得するように投下するのが拡大再生産の特徴だと言うことだと思います。単純再生産では、剰余価値はすべて資本家が消費してしまい、くり返し投資されるのは、回収された元本、資本家自身が過去に労働して稼いだ元本だと言うこともできるが、拡大再生産=資本の蓄積過程ではそういう言い訳できないということです。
マルクスはここで、労働生産物の取得法則または私的所有の法則について、ヘーゲル風の言い回しをします。あとで資本家に成長する生産者も、商品生産の初期段階では自分で労働して生産したものを自分のものとするという当然の取得法則または所有法則にしたがっていたが、資本主義的生産様式の発展とともに(賃労働の普及とともに)対立物に転化する、つまり「所有は、いまや、資本家の側では他人の不払労働またはその生産物を取得する権利として現れる。」(④、p1001)
それは必然的法則的なことだというのです。同一法則によって取得または所有の形態が逆転するということです。労働生産物は労働したものの所有物、生産物は生産者のものという法則から、生産物は生産しない者の物という取得形態に逆転する、これは所有権の乱暴な転覆などではなく、実は商品生産の内的諸法則(等価交換の法則にのっとり、資本家はつねに労働力をその価値どおりに買うが、労働力の使用価値あるいは労働力の消費過程である労働は、労働力の価値を越えて価値を創造する、この超過部分、剰余生産物あるいは剰余価値を、資本家は何も費やさずに取得する)の必然的帰結だというのです。
労働生産物が資本家によって取得される根拠として、一般的には生産手段が資本家の所有物だからと言われてますが、マルクスはここではもっと踏み込んで、賃労働のもとでは資本家は、①生産手段は資本家のもの、というだけでなく、②労働力も価値どおりに買った資本家のものであるからその商品(労働力)の使用価値の消費過程つまり労働すべても資本家のものだ、だから生産物は紛れもなく(法的にも)資本家のものだというのです。(④、p1001~1002) ですから、「否定の否定」つまり社会主義的変革は「生産手段の社会化」という形態上の変革スローガンよりももっと深い「労働と取得の同一性の回復」という抽象的スローガンになるべきです。でも、これでは理解する人がいないでしょう。
不破議長は講義のなかで、これを非常に重視し、これが「否定」であり、弁証法的に「否定の否定」で取得形態が再度変わることを展望している社会主義革命論がここにある、と強調するのですが、どうでしょうか。講義のなかでは「否定の否定」にあたる「個人的所有の再建」論についての資料も使われました。「個人的所有の再建」論については第24章第7節の研究で詳しく触れられますので、ここではこれくらいにとどめます。
さて、第2節では「スミスのドグマ」と言われる誤った価値論から出発した再生産論を批判しています。スミスのドグマとは「商品の価格は労賃、利潤(利子)および地代から、すなわち労賃および剰余価値からのみ構成されていると言うもの」(注32、④、p1014)で、これにもどづくと再生産論は「生産的労働者によって剰余生産物が消費されること」を強調するという点では健全性を示すのですが、「すべての個別資本は不変部分と可変部分に、つまり生産手段と賃金とに分かれるとしても、個別資本の総和、すなわち社会的資本についてはそうではない・・社会的資本の価値は、反対に、それが支払う賃金の総額に等しい、言いかえれば社会的資本は可変資本にすぎない」(訳注*2、④、p1012~1013)という結論です。つまり個別資本では追加資本は労賃と生産手段に分かれるが、社会資本で見るとすべて労賃に支出される、と言うことです。
どうしてかと言うと「たとえば、織物工場主が2000ポンド・スターリングを資本に転化するとしよう。彼は、この貨幣の一部分を職布工の雇い入れに支出し、他の部分を毛糸や毛織機械などに支出する。しかし、彼が糸や機械を買う相手の人々は、さらのその代金の一部をもって労働に支払い、こうして同様のことが次々行われ、ついには、この2000ポンド・スターリングの全部が労賃の支払いに支出される、すなわちこの2000ポンド・スターリングで代表される生産物の全部が生産的労働者によって消費され尽くす、以下同様、というわけである。」(④、p1011~1012) これら、スミスとその弟子たちの言い分を図にすると下のようになります。スミスのドグマが長く継承されたのも、再生産過程の表面的な分析にとどまれば、なるほどそう見えるからです。
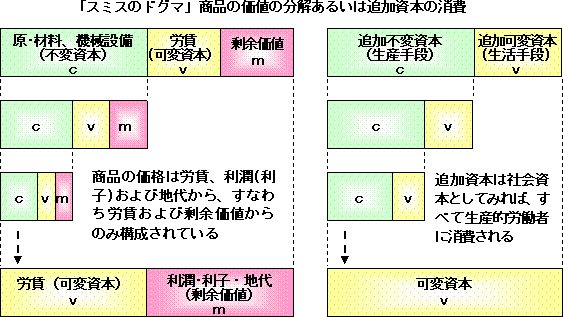
これは大変厄介な問題です。不破議長は「『資本論』全三部を読む・上」の131ページで、「多少とも無限級数のことを知っている方なら、この『以下同様』の議論を無限に進めてその総計を計算しても、資本のすべてが『消費され尽くす』ようなことは起こりえないことは、すぐ分かることです。」と一蹴していますが、ことはそんなに簡単な問題ではありません。この問題を解決するには第2部第3編「社会的総資本の再生産と流通」という再生産論の壮大な展開を待たなければならないくらいの問題です。(もっとも不破さんは事を理解してないわけではありません。「マルクスと『資本論』・上」のp220~230で、この辺を詳しく論じています。)しかし、ここでは深入りをせず、簡単にけりをつけることが大切なのです。
なお、第2節の最後で、ケネーの経済表に触れていますが、それまで第1部の知識しかなかった私は、初めてそれ(ケネーの経済表)を見たとき全く理解することができませんでした。それを理解可能にした、第2部の再生産論の展開こそ、「資本論」のなかで私が一番感動した部分です。しかしそれは、(ドイツ語第3版を基礎としている)現在の資本論には全面的に現されておらず、私も不破さんの最新の研究によってしか、マルクスの再生産論の全体像に触れることができませんでした。
第3節は剰余価値のうちどれくらいの部分が追加資本として再投入されるべきかと言う問題についての古典経済学派や俗流経済学者の色々な主張を紹介します。それに先立ち、マルクスはまず最初に、社会的生産諸力を発展させ、「各人の完全で自由な発展を基本原理とする、より高度な社会形態(共産主義社会*ykb)の唯一の現実的土台となりうる物質的生産諸条件を創造させる」という、資本家階級の歴史的役割についての命題が初登場します。価値論では「より高度な社会形態」について、生産過程に着目した「自由な生産者の結合」という表現が出てきましたが、ここでは再生産過程に関連して資本家階級の歴史的使命を肯定的に捉えています。(④、p1015~1016)
資本家をして「生産のための生産」に駆り立てる、「資本主義的生産様式の内在的諸法則」は価値論の「相対的剰余価値の生産」で出てくるものとだいたい同じです。それは人格化された資本の魂だと言うのですから、資本家個人の思惑(享楽と奢侈の魂)とは無関係にということになります。資本のスローガンは「蓄積せよ!」なのだが、資本家個人の魂は享楽と奢侈への衝動を抑えて蓄積に励むのだと言うのがシーニアの「節欲説」です。シーニアの「節欲説」についてはあとでもう少し詳しく触れます。それにしても1017ページのルターの引用は辛らつでマルクスらしい引用ですね。
では資本家は享楽と奢侈の浪費はしないかというとそうではありません。「節欲」を美徳としていた資本家も、「原罪」を払拭することができず、旧貴族のように享楽と奢侈に走るようになります。しかも資本家の浪費は貴族の開けっぴろげの浪費とは違い、こせこせとした打算に満ちたものになります。(④、p1019) 「交際費」は彼らの浪費の言い訳です。エイキン博士の話(④、p1020~1021)は、すでにおとぎ話にしかなりません。
さて、次は「人口論」で有名なマルサスへのリカード学派の反論を取り上げています。マルサスはリカードとの論争で、地主階級の立場に立ち、過剰生産恐慌を避けるためにも、地主や貴族による非生産的消費が必要だというとんでもない主張をします。これに対しリカード学派の誰か(「今時マルサス氏の主張による需要の性質および消費の必要にかんする諸原理の研究」の著者)がとんでもない不公平だと叫ぶのですが、マルクスは「その彼が『労働者を勤勉にしておくためには』賃金をなるべく最低額に抑えることが必要だと考える。」と皮肉を言います。(④、p1022) なお、これに続く「労働者たちの側からの需要が増大する・・」は「減少する」の誤りではないかと思われます。
1825年にイギリスで人類史上初めての恐慌が勃発して以来、大陸でもイギリスでも労働者の反乱が相次ぎ、早くも資本主義の矛盾が明らかになりつつありました。この時期、サン・シモンやフーリエ、ロバート・オーエンなどの空想的社会主義が普及するなかで、資本主義擁護の俗流経済学の出番が回っていきました。#009:シーニアの「最後の1時間」で論じた、例のシーニア教授は、その前にも「節欲説」という「大発見」をしていました。(④、p1024) これは簡単に言うと、資本家は利潤を自分の享楽のために消費しきってしまわずに、「節欲」して労働者に生産用具として貸し出すのだ、資本の蓄積は資本家の聖徳のたまもだのというものです。資本家弁護も極まれりといういものです。注(四一)にはこれへのマルサスとJ・S・ミルの批判が取り上げられています。
次に続く部分(④、p1027~1028)では、資本主義以前の経済的社会構成体では、資本家や生産手段から分離された労働者が介在しなくても、生産が拡大されていったことを述べています。
第4節は剰余価値が資本と収入(資本家の消費)に分かれる割合、つまり追加資本の大きさは、いろいろな要因で異なるというような、長い表題ですが、主に論じているのは労賃の引き下げによる蓄積の促進です。ここで面白いのは、80年代・90年代を通じて中国など海外へ移転していった資本が、国内で「中国の賃金は日本の10分の1以下、これに打ち勝つ生産性を上げなければ」などといっそうの労働強化と賃金抑制を押し付けてきたのと同じ状況が、当時のイギリスと大陸の関係で語られていることです。
労賃をいかに引き下げるかというための「乞食スープ」や食料品への不純物混和などは第4篇第13章「機械設備と大工業」でも論じられた、資本の無慈悲な仕打ちが告発されています。教区救済金や救貧法についていはあとで触れられることになるでしょう。
1036ページからは労働の弾力性ともいうべき特徴が語られています。生産力が不変のもとでは2倍の生産には2倍の労働が必要だが、必ずしも2倍の不変資本(生産手段=労働対象と労働手段)を必要としません。採取産業では特にそうで、原料は自然に存在し、前貸し資本はいりません。農業では、土地の豊度を高めれば、新たな不変資本の投下なしに、労働者数を増やせば収穫量が増えます。労働者数を増やさず、労賃の割増なしに労働日を延長すれば、(2007・11・19挿入)どちらも自然に対する人間の働きかけが、新たな資本の介在なしに蓄積(剰余価値)を増大させます。
後に論じる再生産論との関係で興味深いのは、採取産業および農業と製造工業との関係を論じた部分です。「・・・採取産業と農業とは、製造工業にたいしてそれ自身の原料とその労働手段の原料とを提供するので、前者(採取産業および農業*ykb)が追加的な資本の提供をまたないで生み出した生産物増加分は、製造工業を利することになる。」「資本は、富の二つの原形成者、すなわち労働力と土地(自然*ykb)とをみずからに合体することによって膨張力を獲得するのであって、これにより資本は、一見すると資本自身の大きさによって定められてた限界を超えて、すなわち資本の定在形態たる、すでに生産されている生産手段の価値および総量によって定められた限界を超えて、自己の蓄積の諸要素を拡大することができる。」(④、p1038)
次の部分も大変興味深いところです。競争は、機械設備の償却を早くしようと資本家に強制し、結局それは労働者への搾取を強めることになるというところです。(④、p1040) つまり、機械設備の価値は、それが競争で失われるまえに、なるべく早く生産物に移転したいので、交代勤務で昼夜連続生産をしたがるわけです。
次は「資本論」第2部(再生産論)にかかわる結論的な部分です。「新価値を創造しながら旧価値を維持するということは、生きた労働の天分である。それゆえ労働は、その生産手段の効果や規模や価値の増大につれて、したがって労働の生産力の発展にともなう蓄積につれて、絶えず膨張する資本価値を、つねに新しい形態で維持し、永久化する。」(④、p1041~1042)
第5節は「労働元本」すなわち労働者の生活手段の総量は固定したものだとする俗流経済学のドグマへの批判です。マルクスは書いていませんが何となく社会的総資本は結局は労賃の総額に等しいという「スミスのドグマ」に端を発しているような気がします。蓄積や拡大再生産が見えず、労働者の運命に無頓着な俗流経済学者には、「労働元本」(=賃金総額)は不変の一定額にとどまっている方が、都合がよいわけです。
次は第23章ですが、その前に何か面白い話をしましょう。
2004年11月1日 ykbdata
|トップページ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|