◆◆◆「資本論」の研究◆◆◆
|トップページ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#008:絶対的剰余価値の生産
第3篇第5章 労働過程と価値増殖過程 では、商品の生産過程を、労働の二重性から、一方では「労働過程」、また一方では「価値増殖過程」として分析します。(②、p318~319)「第1節労働過程」は具体的有用労働がまずは自然的素材に働きかけて使用価値を生産する、「生産過程」の具体的側面です。
第1節 労働過程 「労働過程」には具体的有用労働、労働対象、労働手段が含まれています。労働が働きかける対象(「労働対象」)はすでに自然的素材から形を変え、それ自体も労働生産物である「原料」であることがあります。たとえば、綿紡績労働の対象である綿花は自然的素材ですが、綿織物労働にとっての綿糸はすでに自然的形態を脱した「原料」です。労働手段は具体的有用労働と労働対象の間にあって、労働の労働対象への働きかけに役立つ手段です。(②、p305~306)簡単に言えば、綿紡績労働は、綿花(労働対象)と綿紡績機(労働手段)が必要ということです。
労働対象と労働手段はともに労働過程に入り込み、生産的に消費される「生産手段」です。生産手段は生産的労働に消費され、新たな使用価値の形成要素となります(「生産的消費」)。ここで面白いのは「死んだ労働」と「生きた労働」です。原料や労働手段(生産手段)は過去の労働の成果で、言わば「死んだ労働」です。しかしこれは直接の使用価値を持っていません。こうした「死んだ労働」に息を吹く込んで現実の使用価値によみがえらせるのが「生きた労働」だとマルクスは言っています。(②、p313)しかし、価値増殖過程では「生きた労働」が「死んだ労働」に支配されることになります。
労働過程の結果はどうなるでしょうか。生産手段も資本家のもの、労働力も資本家が購入した、資本家のもの。したがって生産物も資本家のものという理屈になります。(②、316~317)
第2節 価値増殖過程 商品の生産過程を、抽象的人間労働の観点から考察すると、それは「価値形成過程」、剰余価値生産に視点を向ければ「価値増殖過程」としてとらえることができます。第1篇第1章で学んだように、商品は価値論から言えば、使用価値と価値の分裂とその統一としとらえますから、商品の生産過程は、(具体的有用的な)労働過程と価値形成過程の分裂とその統一ととらえることができます。(②、p318~319)
(具体的有用的な)労働過程としては、すなわちどのような具体的生産手段によって、どんな具体的な労働を行い、どんな使用価値を生産するか、すなわち労働の質が問題とされました。しかし、価値形成過程としては、労働の質は捨象(度外視)され、社会的必要労働の時間、労働の分量が問題となります。ここでマルクスは計算例を出します。
マルクスは微分・積分など高等数学は得意でしたが、加減乗除、つまり計算が苦手で、価値の計算例はむずかしいものは出てきません。マルクスの計算例を見てみましょう。綿紡績労働の例です。
労働力の日価値が3シリングで、これが6時間の労働を表しているとします。6時間で紡ぐ綿花は重さ10ポンドで10シリング、10ポンドの花を紡ぐときの労働手段の磨耗を紡錘で代表し、その磨耗分を2シリングとすると、6時間、9時間、12時間の労働生産物の価値は右の表のようになります。それぞれ剰余価値が0、1.5、3シリングとなり、またそれぞれ0、3、6時間の剰余労働(不払労働)に対応しています。もし、労働日が12時間とすれば、彼は20ポンドの綿花を紡ぎ、労働手段を4シリング消費し、彼の労働は、労働力の価値3シリングをこえて、12時間で6シリングを生産物に付け加え、新たに3シリングの剰余価値を生み出し、これが資本に転化します。こうして、労働日が労働力の価値の等価物を生産する点を超えて延長されるやいなや、労働過程は価値増殖過程にります。(②、p333~334)
第6章 不変資本と可変資本 これは「#004:中間産品に使用価値はあるか」で先行的に取り上げましたが、もう少し詳しく見てみましょう。生産手段の価値の生産物への移転は、労働過程中に行われます。労働は新たな価値も付け加えるわけで、労働はふたつ仕事をするわけです。これまでの論議でもうすでに明らかのように、生産手段の生産的消費によって生産物にその価値を移転するのは、労働の特殊的(具体的)有用的性格であり、労働が新たな価値を生産物に付け加えるのは、労働の抽象的人間的性格によるものです。言い方を変えれば、具体的有用労働が生産手段の価値を生産物に移転し、抽象的人間的労働が新たな価値(労働力の価値およびそれを超える剰余価値)を生産物に付け加えるのです。労働力の価値を生産するに必要な時間を超えて労働日(一日の労働時間)を延長し、剰余価値を生産することを「絶対的剰余価値の生産」と言います。(②、p341~342)
労働過程の立場から見る生産手段と労働力という資本構成上の区別は、価値増殖過程の立場からは「不変資本」および「可変資本」として区別されます。生産手段の消費と生産物への価値移転は、「不変資本」がある使用価値の姿態を脱ぎ捨て、別の使用価値の姿態をまとう過程であるととらえます。(②、p356)第5章の終わりの部分は、第2部のはじめの章、資本の有機的構成への伏線があります。(②、p358~359)
第7章 剰余価値率 第1節では、これまでの理論展開に立って、労働者に対する搾取の強度について「剰余価値率」という概念を規定します。これは労働者の立場に立った見方で、資本の側から見ると「利潤率」となります。
6章の内容を、数字を使った例にしたのが7章第1節です。それは次のようになります。まず、前貸資本C(Capital))が生産手段(労働対象=原料と機械・用具)に支出される不変資本c(constant)と労働力に支出される可変資本v(variable)に分解され、剰余価値m(mehrwert)が得られるとします。つまり、生産過程に投入される資本はC=c+v、生産過程から出てくる生産物価値はC´=c+(v+m)となります。これを労働者の立場で、価値増殖過程としてみるとv->(v+m)となり、剰余価値率m/vは、マルクスの例で100%となり、搾取の強度を表します。(下表2段目)
逆に資本の視点に立てば投下した資本に対する利潤の割合、すなわち利潤率m/(c+v)がいつも問題になります。マルクスの例では利潤率m/(c+v)は18%となります。しかし、c+v->c+(v+m)で不変資本cは使用価値の姿態は変わりますが、価値の大きさは生産過程を通して不変ですから(だからこそマルクスによって不変資本と名づけられたのです)価値増殖過程としては関与しません。c(機械・用具+原料の価値)が大きい近代産業ほど、価値増殖の割合、すなわち搾取の度合いを覆い隠します。(上表3段目)不変資本、可変資本の区別に対し、ブルジョア経済学は固定資本(機械・用具)、流動資本(原料・労賃)という把握にとどまり、価値増殖過程の把握をしませんので、どうしても剰余価値率まで到達できません。(私のカッコの使い方は、不変部分と可変部分を区別する意味で、マルクスと違いますが、このほうが分かりやすいと思います。)
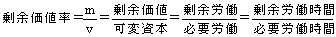
第2節は、第5章第2節の綿紡績労働の例をとって、不変資本、可変資本(労賃)、剰余価値のそれぞれが、下表のように、その構成比率に比例した生産物の量で表されることを述べています。しかし、これは生産過程を時系列的に区別するものではありません。どこからどこまでがの生産物が不変資本分あるいは労賃分、剰余価値分ということではありません。 同一の労働日のうち、1時間あたりを考えれば、表に示した価値構成諸要素は、それを表す生産物の量でも、それを表す価値額でも、それぞれ12分の1に比例的に配分され、表現されます。つまりどの時点での労働も、比例的に一様に諸価値を移転・付加します。それはNとSに分極した棒磁石を、いくつかに細分しようとも、同じようにN極とS極の関係は変わらないのと同じです。
次は第3節、有名な「シーニアの『最後の1時間』」です。
2002年5月27日 ykbdata
|トップページ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|