◆◆◆「資本論」の研究◆◆◆
|トップページ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|#019:「本源的蓄積」、救貧法と「人口論」
さて、今回は「いわゆる本源的蓄積」と「近代的植民論」を簡単にかたずけて、懸案の「人口論」についての研究を行いたいと思います。
第24章 いわゆる本源的蓄積 は「資本論」のなかでも重要な章だと思います。第1節 本源的蓄積の秘密 でマルクスは、まず蓄積が先か資本主義的生産様式が先か、つまり「鶏が先か、卵が先か」の堂々めぐりから抜け出すためには、「先行的蓄積」とアダム・スミス言うところのもの、「すなわち資本主義的生産様式の結果ではなくその出発点である蓄積を、想定するよりない。」と論議の方向付けをします。
マルクスは「いわゆる本源的蓄積は、生産者と生産手段との歴史的分離過程にほかならない。それが『本源的なもの』として現れるのは、それが資本の、そしてまた資本に照応する生産様式の前史をなしているためである。」(④、p1224)と述べ、貨幣の蓄積や資本家の登場ということではなく、農民がすべての生産手段と生活手段から引きはがされて「自由な労働者」になるということが本源的蓄積の中心問題であるとして、資本家のたまご達の、ギルドや封建領主へのたたかいについては、あまり焦点を当てません。
ギルド(「社会科学総合辞典」より)
徒弟制度を伴う同職組合。中世ヨーロッパの都市で11世紀発生した商人ギルドは、仲間で企業者の数や商品の価格・品質・販売数量・販売方法を協定した。ギルドは商工業者中心の中世都市の自治をうちたてた。13世紀ごろからは手工業者ギルド(ドイツではこれをツンフトという)が発展し、封建領主と結託した豪商と対抗して市政民主化の運動を展開した。ギルドは、中世商工業の基本的組織であったが、後期になると排他的・独占的な団体となった。封建制末期に資本主義的生産関係が発展するにつれて、ギルドはくずれさった。日本では、座(平安末期・鎌倉・室町・戦国時代)、株仲間(江戸時代)と呼ばれる同職組織があった。
ということで、「本源的蓄積」は、はじめの資本家はどう生まれたかというよりは、どうして「自由な労働者」が出現したか、つまり農民や手工業者がどうやって土地や仕事場などの生産手段から引きはがされたのか、という視点のほうが大事です。(資本はすでに中世ヨーロッパでも、商人資本、高利貸資本として存在していたのです。)
この問題を思想上の論争としてみると、なぜいま少数の富者と多数の貧民がいるのかという問題になります。ブルジョアたちからすると「はるかに遠く過ぎ去ったある時代に、一方に勤勉で聡明で、とりわけ倹約な選ばれた人がいて、他方には、怠惰で、自分のものすべてを、またそれ以上を消費し尽くす浮浪者たちがいた。」(p1222)のが始まりだというわけですが、マルクスは、そうではない、生産者が生産手段から引きはがされる過程は「血と火の文字で人類の年代記に書き込まれている。」(p1225)、つまり暴力的に行われたと断じています。
第1節には都市と農村の関係や都市国家のことなど、興味深い記述がいっぱいあって、ykbdataもかなり調べまわりましたが、本題でないので省略します。マルクスは第1節の最後に、本源的蓄積の中心問題は農民からの土地の収奪だ、その典型としてまたもやイギリスを例にとろうと言います。
第2節 農村民からの土地の収奪
まずマルクスは、すでに封建制が崩壊していた15世紀の農村の、のどかな様子を描いています。これを模式的な絵にしてみると下のようになります。
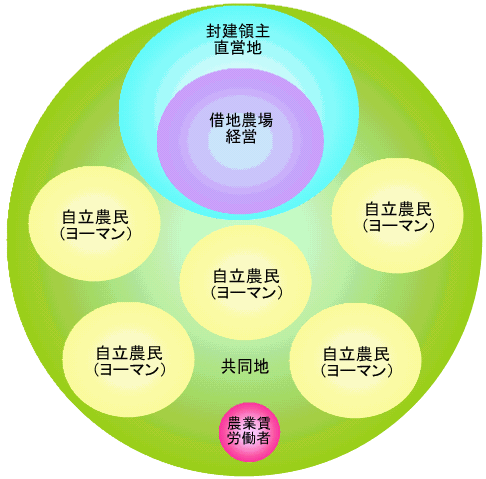
問題は、最下層の農業賃労働者さえも「・・・彼らは自分たちの賃金のほかに四エーカーまたはそれ以上の広さの耕地と"小屋"を割り当てられていたからである。そのうえ、彼らは本来の農民(自立農民)とともに共同地の用益権を享受していて、そこでは彼らの家畜が放牧されていたし、またそれは同時に彼らの燃料になる薪(たきぎ)や泥炭などを供給していた。」(p1227~p1228)ので、このままでは「自由な労働者」にはなり得ないということです。
4エーカーと言えば、4,050㎡つまり40.5アール、坪数で言うと約1,200坪です。
ところが、15世紀末に羊毛マニュファクチュアの繁栄による羊毛価格の騰貴を契機にして、牧羊地の確保のために「農民をその土地から暴力的に狩り立てることによって、また農民の共同地を横奪することによって」(p1230)一挙に大量に「自由な労働者」をつくり出したのです。この中で自立農民は羊毛マニュファクチュアなどの産業資本家とその労働者(「自由な労働者」=プロレタリアート)に分裂して行きます。「第一次囲い込み運動」と呼ばれる、この収奪は以後17世紀中頃まで1世紀半にわたり、イギリス史に「血と火の文字」で書き込まれたのです。
これ対して絶対王政は「囲い込み」を禁止しましたが、効果はありませんでした。政治的にも経済的にも実権を握っていた地主と借地農場経営者は結託し、"小屋"の破壊と農民追い立てを暴力的にすすめました。なぜなら「わずか数エーカーでも"小屋"につけられるなら、労働者をあまりにも独立させることになるから」(④、p1233、ハンター博士談) 「囲い込み」は牧羊地の拡大であると同時に、農民を土地から引きはがして「自由な労働者」に転化させる運動だったわけです。
その後の、土地からの農民の引きはがしと追い立ての大きな契機として、宗教改革によるカトリック教会領の解体(p1234~1235)、17世紀のスチュアート王政復古のもとでの立法による国有地(王領)の私有地化(「名誉革命」でいっそう拡大、p1238~1239)、15世紀末からも個人的に行われていたが18世紀には法律(「共同地囲い込み法」、1709年制定)によって行われるようになった共同地の横奪(p1241~1248)、そして最後に19世紀のいわゆる"地所の清掃"(スコットランドの例で説明されている、p1248~1250)があげられています。
横奪される土地は教会領であったり国有地(王領)であったり、あるいは共同地であったりしますが、共通するのは、名義上は領主や教会の土地であっても実態は農民に分配されていた土地を、大土地所有者の「私有地」に転化して行ったこと、すなわち封建的土地所有から資本主義的土地私有に強制転化されたことです。同時にその土地から農村民を暴力的に追いたて「鳥のように自由な労働者」を一気に大量に生み出したことです。
マルクスはこれらについて、「囲い込み」の推進者や批判者にいろいろ語らせていますが、代表者として二人の経済学者の弁を例に出しましょう。まずは「囲い込み」に批判者的なプライス博士の弁。「もし土地がごくわずかの大借地農場経営者の手に帰するならば、小借地農場経営者」(以前には彼はこれを「自分が耕す土地の生産物によって、また自分が共同地に放牧する羊や家禽や豚などによって、自分自身と家族を扶養しているので、生活手段を買う機会をほとんどもたない一群の小土地所有者と小借地農場経営者」と呼んでいる〔マルクスの説明*ykb〕)「は、他人のための労働によって生計を維持しなければならないような、そして、自分の必要なものはすべて市場で求めざるをえないような人々に転化される。・・・これこそ、借地農業の集中が自然の成り行きで作用する仕方であり、また、多年来この王国で実際に作用してきた仕方である。」(p1244)
今度は"囲い込み"の擁護者でプライス博士の反対者であったJ・アーバスナットとか言う著者の言葉を聞いてみましょう。「開放耕地で自分の労働を浪費している人々がもう見られないからといって、人口が減少したと考えるのは、正しい結論ではない。・・・小農民を他人のために労働しなければならない人々に転化することによって、もっと多くの労働が流動されるとすれば、それこそ、国民」(そのなかにはこの転化させられた小農民はもちろんはいらない〔マルクスの説明*ykb〕)「が希望するに違いない利益である。・・・彼らの結合労働が一つの借地農場で使用されれば、生産物はもっとふえるであろう。こうして製造業のための余剰生産物が形成され、それによりこの国民の金鉱の一つである製造業が穀物の生産量に比例して増加する。」(p1246) 「本源的蓄積」とは何か、なんと正直な告白でしょうか。
最後にマルクスは本源的蓄積の中心問題である土地からの農村民の引きはがし(「囲い込み」)についてまとめています。「教会領の略奪、国有地の詐欺的譲渡、共同地の盗奪、横奪による、そして容赦のない暴行によって行われた封建的所有および氏族的所有の近代的な私的所有への転化、これらはみんないずれも本源的蓄積の牧歌的方法であった。これは、資本主義的農業のための場面を征服し、土地を資本に合体させ、都市工業のためにそれが必要とする鳥のように自由なプロレタリアートの供給をつくり出した。」 さて、「牧歌的」とはどういうことなのでしょうか。
第3節 15世紀末以来の被収奪者にたいする流血の立法。労賃引き下げの諸法律(第3節が「流血の立法」というわけですから、第2節は「火の追いたて」ということで、「血と火の文字」なのでしょうか。)
さて、土地からの農村民の暴力的な追い立てさえ「牧歌的(中世的*ykb)方法」だということは、「流血の立法」は近代的(資本主義的)方法だというのでしょうか。「火の文字」で歴史に書き込まれた、土地からの農村民の暴力的引き剥がしは、本源的蓄積の中心問題でしたが、それだけでは資本主義的生産様式の本格的発展には不十分でした。長い間、封建的諸関係のなかで生きてきて、突然新しい事態に直面した「鳥のように自由なプロレタリアート」も、すぐには賃労働者になれなかったし、なる気もありませんでした。彼らはただ放浪し、乞食や盗賊になったというのです。(④、p1258) 彼らを賃労働者とするために、浮浪自体の処罰と賃労働の強制のために、15世紀から16世紀の西ヨーロッパ全体で浮浪者に対する流血の立法が行われました。
以下、ヘンリー8世治下の1530年の立法、エドワード6世治下の1547年の立法、エリザベス1世治下の1572年の立法、ジエイムズ1世治下17世紀初頭の立法・・・。浮浪と不就業を鞭打ちや焼印で処罰し、「再犯」は処刑するという、文字通り「流血の立法」は18世紀まで有効でした。(p1258~1262) マルクスは「こうして、暴力的に土地を収奪され、追放され、浮浪人にされた農村民は、グロテスクで凶暴な法律によって、鞭打たれ、烙印を押され、拷問されて、賃労働者に必要な訓練をほどこされた。」と述べています。
十分に発達した資本主義的生産様式のもとでは、こうした「経済外的な暴力」は例外的で、「生産の自然法則」で労働者を支配し続けることができるが、資本主義的生産の歴史的創生期は違う、労賃を「調整する」ため、また労働日を延長するためには国家権力を使った、これこそ本源的蓄積の一契機だ。(p1263) ということで、今度は労賃の抑制と労働日の延長を強制する立法についてです。
マルクスは、農村民の追放について述べる前に15世紀の農村ののどかな様子を描きましたが、ここでもまずはその経済的内容を明らかにします。すなわち、「14世紀の後半に発生した賃労働者の階級は・・・農村の自立的農民経営と都市の同職組合組織とによって強くその地位を保護されていた。・・・資本の可変的要素〔可変資本、労賃*ykb〕は不変的要素〔不変資本、生産手段*ykb〕よりもずっと重きをなしていた。それゆえ、賃労働に対する需要は、資本が蓄積されるにつれて急速に拡大した。他面、賃労働の供給は、緩慢にしか需要についていかなかった。」(p1264) つまり労働者の生活は保護されていて、「労働市場」は売り手市場だったというわけです。
さて、一連の立法ですが、エドワード3世治下1349年の"労働者規制法″までさかのぼり、1563年のエリザベス徒弟法など、これらは法定賃金より高い賃金を禁止し罰するものです。1360年にはレンガ積み工や大工の団結を禁止し、ジョージ2世の時代(1727年~1760年)には団結の禁止をすべての製造業に拡張しました。(p1265~p1266)
次にマルクスは、本来のマニュファクチュア時代はもう経済法則だけで(つまり資本主義的蓄積の一般的法則の作用だけで)賃労働への支配は可能になったが、資本家は「非常時にそなえて、古い兵器庫の武器なしにはすませようとは望まなかった」と言います。つまり、念のために最高賃金を制限する法律がその後も作られ続けたということです。ところが、18世紀には逆に最低賃金を定める法案が提出され、ついに1813年には400年にわたった賃金規制の諸法律が撤廃されました。(p1267~1268)
これは資本家が人道的になったからではないんだ、工場主の私法での支配と、資本家が払う救貧税による賃金の絶対的不足への補填制度(スピーナムランド制、1790年代より行われる)によって、賃金規制の法律が意味をなさなくなったからだというわけです。つまり、下げるられる限界を超えて賃金抑制がすすんだということです。
次に前回も触れた団結禁止法についてのべています。ブルジョアは、封建勢力を打ち負かすまでは労働者階級を利用するが、支配権を確立すると労働者に敵対して労働組合もストライキも犯罪として取り締まるようになる、団結禁止法は廃止されたが、この点での労働者規制法規は根強く残っているというわけです。
第4節 資本主義的借地農場経営の創世記
この節の主題は「資本家たちは本源的にはどこから来たのか?」(④、p1271) です。マルクスは借地農場経営者の出自を中世の荘園管理人(農奴)までさかのぼり、それが貨幣で大地主に地代を払う本来の借地農場経営者に発展する歴史を簡潔に述べています。(p1272)
次に15世紀後半から借地農場経営者が資本家に成長する過程が描かれています。つまり農業の変革(「農業革命」)と貨幣価値の変動による「本源的蓄積」です。これは貨幣地代を前提とします。(p1272~1273)
第5節 工業への農業革命の反作用。産業資本のための国内市場の形成
前節まで、「自由な労働者」と「本来的借地農場経営者」(資本家)がどこから来たかを論じました。この節は、そうした「本源的蓄積」の経済学的イメージのつかめる大切な節です。
マルクスはまず、価値論で述べます。自給自足だった食料は、少数の耕作者によって生産され商品として市場に出され、可変資本の素材的要素に転化する。農民の生活手段で同じく自給自足だった亜麻も、工業材料として不変資本の一要素に転化したのです。(p1276~1278)
次に今度は「集積」論で描きます。これが「本源的蓄積」の具体的イメージがつかめるので、マルクスの言葉をそのまま繰り返して見ましょう。
亜麻は、いまでは、マニュファクチュア経営者の不変資本の一部をなしている。それは、以前は、それを自分で栽培して家族とともに少しずつ紡いでいた無数の小生産者のあいだに分配されていたが、いまでは、自分のために他人に紡がせたり織らせたりする一人の資本家の手に集積されてる。亜麻紡績工場で支出される余分な労働は、以前は無数の農民家族の余分の収入として、あるいはまた、フリードリヒ二世の時代には、"プロイセンの王のために"〔なんの見返りもなしにの意〕租税として実現された。いまではそれは少数の資本家の利潤として実現される。紡錘や織機は、以前は広く農村に分散されていたのに、いまでは労働者と同じように、また原料とも同じように、少数の大きな作業場に詰め込まれている。そして、紡錘や織機や原料は、紡ぎ手や織り手の独立した生存の手段から、いまでは、彼らを指揮して彼らから不払労働を吸い取るための手段に転化している。大マニュファクチュアを見ても、大借地農と同じく、それらが多くの小生産者の合成されたものであり、多くの小独立生産者の収奪によって形成されたものであることはかわらない。(p1277~1278)
「生産者と生産手段の分離」というわけですが、同時に労働者は食料などの生活手段からも分離されるわけですから、労働者は市場でそれを購入しなければならず、「農村民の一部分の収奪および追放は、労働者とともに彼らの生活手段と労働材料とを産業資本のために遊離させるだけでなく、国内市場を作りだす。」のです。(p1279)
しかし、市場は作り出しても、市場全体をマニュファクチュアが征服するわけでなく、都市の手工業と農村の家内工業をすべて駆逐して国内市場を征服するのは、機械制大工業によって初めてなされるというわけです。(p1281)
第6節 産業資本家の創世記
「産業資本家」とはここでは工場主を表します。中世に高利資本と商人資本はありましたが、これらは農村では封建制度によって、都市では同職組合制度によって産業資本家への転化を妨げられていました。しかし、封建制度の解体とともに、マニュファクチュアが田園や輸出港に出現しました。こうしたマニュファクチュアの勃興と、アメリカでの金銀鉱山の発見、奴隷貿易とイギリスによる東インドの征服などが本源的蓄積の契機となりました。(p1283~1285)
簡単に言えば、マゼラン(16世紀初旬、世界一周を試み、フィリピンで原住民の王に殺されたという)などに象徴されるような「大航海時代」の征服戦争と植民地化が、本源的蓄積の契機となったということです。これを時代的に追ってみると、スペイン、ポルトガル、オランダ、イギリスの順で、ここでも暴力が主役となりました。(p1286)
植民地では独占、詐欺、暴力によって錬金術のように本源的蓄積がすすみ(p1288)、成長するマニュファクチュアの販路を拡大しました。コステス(1521年に中米のアステカ文明を滅ぼしたスペイン人)などの略奪によって獲得された財宝は、本国で資本に転化しました。植民地制度を真っ先に発展させたオランダは、17世紀中葉には商業的繁栄の頂点に立っていました。(p1290)
次に国債制度が本源的蓄積をいっそう促進すること、国債発行の必然的結果としての生活必需品に対する過重課税が述べられています。しかも、それが農民や手工業者を暴力的に収奪するというのです。何か今の日本の国債発行による大型公共事業と、そのツケ回しである消費税のことを言われているようです。現在の日本でも、農家と中小業者が、消費税増税と免税点の引き下げで、たいへんな事態に陥ろうとしています。
そして次に銀行制度が、さらに資本輸出が本源的蓄積の源泉として登場し、保護関税と輸出奨励金と続きます。(p1292~1295) これらはすべて、国家によるものです。
本源的蓄積の獣的な衝動の列挙はまだ続きます。今度は大工業の幼年期での「幼児誘拐」と「幼児売買」、そして死ぬまで働かされた陰惨な搾取です。(p1296~1298) ここでも教区の"労役所"=救貧院が登場します。幼児労働の残虐さは第3篇8章「労働日」でも、第4篇13章「機械設備と大工業」のところでも論じられていますが、それは法律によって規制されていない時代の経済法則的なものでしたが、ここで論じられているのは経済法則外の「誘拐」と「人身売買」、そして殺人的搾取です。つまり今で言う「幼児虐待」の犯罪的搾取です。
マルクスは、児童の命をすり潰してでも蓄積を推進する、こうした「人狼的」渇望について、「マニュファクチュア時代を通じて資本主義的生産が発展するにつれ、ヨーロッパの世論は羞恥心や良心の最後の残りかすまで失ってしまった。」と告発し、奴隷貿易に触れたあと、次の苛烈な言葉でこの説を結びます。
「資本は、頭から爪先まで、あらゆる毛穴から、血と汚物とをしたたらせながらこの世に生まれてくる。」
第7節 資本主義的蓄積の歴史的傾向
この「いわゆる本源的蓄積」の章では、①「自由な労働者」の起源(2節、3節)、②資本主義的農業(農業資本)の起源(4節)、③これらの産業資本への影響(5節)、④産業資本の起源(6節)と順次展開してきたわけで、この節ではは「いわゆる本源的蓄積」のまとめの部分です。しかし、「個人的所有の再建」など、いまでも論争のタネになっている未来社会論を含む重要な節です。
最初にマルクスは、本源的蓄積すなわち資本の歴史的な創世記とは、直接生産者の収奪すなわち自分の労働にもとづく私的所有の解消を意味する、と端的に結論します。そして、自立農民にしても手工業者にしても、生産手段の私的所有が熟練と工夫のなど自由な個性が発揮される土台だといいます。(p1303および訳注*1) こうした生産手段の分散、すなわち封建制度のもとでの自給自足経済は、生産手段の集積すなわち資本主義生産の発展を阻止する(p1304)、 本源的蓄積は、個々の生産者の手もとにある生産手段を暴力的に集積することだ、というわけです。
次に本源的蓄積によってひとたび資本主義的生産様式が確立されれば、今度は集中によって資本家の私的所有が収奪されることになる。そして資本主義的生産様式はどんどん発展し、ますます労働が社会的となり、労働者の反抗も増大する、生産手段の集中と労働の社会化が資本主義的生産様式と両立できなくなる一点に達すると社会主義革命で資本主義の外皮が「粉砕される」というわけです。そして、資本主義は封建制のもとでの個人的な私的所有の最初の否定であり、資本主義が否定される未来社会は、生産手段の共有にもとづく「個人的所有を再建する」、これは弁証法の「否定の否定」の法則だというわけです。(p1305~1306)
マルクスは「私的所有」と「個人的所有」と言葉を変えて、資本主義的所有と未来社会の所有形態を明確に区別し、ていねいに「生産手段の共有にもとづく」と言っているのですから、未来社会で「再建される」所有は、個々人の生活手段、享楽手段であることは明らかです。例えば、過去の手工業者にとっては生産手段であるかもしれない日曜大工の工具も、現在すでにそうなっているように、創意工夫で生活を楽しむ享楽手段になるでしょう。ところが「個人的所有の再建」はけしからんという人がいるそうなのですから不思議です。
原注252(p1307)では、過渡期は短いとか、小生産者は反動的だとか、レーニンが読んで早合点したであろう、「共産党宣言」の引用があります。
第25章 近代的植民理論
この章は、本源的蓄積とは何かということを、逆説的に証明する「本当の植民地、すなわち自由人の移住によって開拓される処女地」についてのべています。簡単に済ましましょう。つまり、土地がほとんど無償で自由に手に入る北アメリカでは、資本の本源的蓄積はすすまない、「自由な賃労働者」としての移民も、絶えず自立農民に転化するので、イギリス本国とは違い、つねに労働の不足状態が続き、資本主義的生産は発展しないのです。(p1314~1315)
これに対してウェイクフィールドは、国家の法で北アメリカの土地を高く売りつければ、移民たちは、それを買うために賃労働をせざるを得ない。そしていよいよ土地を購入すれば、つまり国家が土地を売った収入で、次の移民を送り、同じように資本のための賃労働を供給し続けることができるという、「組織的移民」を主張するというのです。(p1321) そうしたことを正直に告白せざるを得ない北アメリカの状況が、本源的蓄積の秘密を、逆説的に証明しているわけです。
第1部突破!
さて、第一部が終わりました。研究の開始から5年の歳月が過ぎました。激しいたたかいの日々の中で2年間のブランクが生じる期間もありました。このテーマを「『資本論』の研究」と、あえて「研究」としたのは、現在の日本社会とのかかわりで論じたいということと、マルクスが何をいいたかったのか、深く考えようと思ったからです。第一部を締めくくるにあたり、マルクスが怒りを燃やしたマルサスの「人口論」とそれにもとづいて大改悪された「救貧法」についての研究をまとめて終わります。
イギリス救貧法の歴史
まず、イギリス救貧法の歴史を見てみましょう。封建制の崩壊の過程で「絶対主義」という王政復古が始まった頃、第1次囲い込み運動もはじまりました。前にも述べたように、土地から追い立てられた農民は、すぐには賃労働者にならず、放浪していました。地方を視察したエリザベス一世女王は、「王国に乞食が満ち溢れいる」ことに驚き、1601年旧救貧法を成立させました。これにより救貧は、教区の義務であり、貧民は救済を権利として要求するようになりました。貧民は女王を「愛すべきベス」と呼びました。
この旧救貧法では、労働能力のあるすべての貧困者の就業と、労働能力をもたない貧困者の救済を主な内容としていました。多子や私生児の扶養も含め、賃金の不足分が救済基金から補填されました。まさに、現在の生活保護にあたります。いま政府が生活保護費を圧縮しようとするように、歴代のイギリス政府も資本主義的生産様式が発展するにつれて、あるいは飢饉や不況で増加する救貧基金を何とか抑えようと、いろいろな「改革」を試みました。
例えば、1662年の「居住法」(マルクスの言う「定住法」*ykb)は、年家賃10ポンド未満(つまり「小屋」*ykb)に住む来住者について、40日以内に教区の負担となりそうな者の送還を命ずる権限を治安判事(借地農場経営者*ykb)に与え、何とか教区の救貧基金の増加を抑えようとしました。また、1722年のナッチブル法は「ワークハウス」への収容を救済の条件としました。(河出書房、世界思想教養全集⑤「イギリスの近代経済思想史」、p44)
ところが、王党派の労働者懐柔戦術もあり、1782年のギルバート法は、労働能力のある貧民に対する院外扶助を認め、1795年のウィリアム・ヤング法は、ナッチブル法のワークハウス条項を廃止し、就業者の賃金補填を内容とする、「スピーナムランド制」を事実上承認しました。こうした「温情主義」と不作や不況、そして反ジャコバン戦争による生活必需品の騰貴の影響で、1790~1818年に急激な救貧税と救貧支出の膨張(それまでの3~4倍*ykb)が生じ、救貧法廃止論が大土地所有者とブルジョアの間で広まりました。(同前、p45)
その後、救貧税の膨張はやみましたが、スウィング一揆などを契機に、「労働者を甘やかし、横柄な態度を助長する」公的救貧の廃止論が再燃し、1834年に新救貧法が成立しました。新救貧法の内容は
①中央救貧委員会の設置
②教区連合と教区救済委員会の設置
③ワークハウス内での救済の原則
④劣等処遇の原則
⑤移民費用の捻出
新救貧法成立の主役は、例のシーニアとチャドウィックでした。シーニアはマルサスの影響を受けていましたが、救貧法廃止の立場をとりませんでした。(同、p55~56)
新救貧法の内容をみると、④は明らかにマルサスの主張でもありますが、④も含め全体的に救済事業の効率化、いまでいう合理化を主張したベンサムの影響が大きかったようです。チャドウィックはベンサムの影響を受けていましたが、院外救済を制限した点ではマルサスの主張に沿ったものとなりました。
結論的に言うと、新救貧法はスウィング一揆などによる、地主中心の支配秩序の揺るぎを回復することが求められる状況で成立しましたが、結果的には「自由な労働市場」を創り出すことを目指したものになりました。さて、次に、マルクスが「貧困処罰所」と呼んだワークハウス=救貧院における「劣等処遇」の苛烈な実態を見てみましょう。
救貧院の実態を鋭く告発したのは、エンゲルスの「イギリスにおける労働者階級の状態」です。エンゲルスは1840年代のマンチェスターの労働者街を次のように描写しています。「ここで背景をかたちづくっているのは、貧民墓地と、リヴァプールリーズ鉄道の停車場と、そのうしろにある貧民労役所、すなわちマンチェスターの『救貧法バスティーユ〔牢獄〕』であって、この労役所は、まるで丘のうえの城砦のように、高い塀と銃眼のあるのこぎり壁のうしろから、威嚇するように、向かいの労働者市区を見おろしている。」(国民文庫、「イギリスにおける労働者階級の状態1」、p130)
エンゲルスは「イギリスにおける・・」の最後の章である「プロレタリアートにたいするブルジョアジーの態度」のなかで、この「救貧法バスティーユ」のなかの実態を次のように告発しています。「食物は、最も貧しい就業労働者の食物より悪く、一方仕事はそれよりもはげしい。・・・監獄の食物でさえ、一般にこれよりもりっぱである。そこで貧民労役所の居住者は、しばしば監獄にはいりたいばかりに、故意になにかの犯行をおかす。・・・労役所の外の友人や、親類からの贈り物をもらうことも禁止されている。・・・かれらの労働が、もしかして個人事業と競争するようなことのないようにするために、彼らには、たいていずいぶんむだな仕事があたえられる。成年男子は、『たくましい男が骨折って一日にやれるだけの』石を割る。・・・『余計者』がふえないようにし、あるいは『堕落した』両親が子供たちに感化をおよぼすことのできないようにするために、家族はばらばらにきひはなされる。・・・グリニッジの救貧労役所で、1843年の夏、五歳の少年が三晩のあいだ、罰として死体置き場に監禁され、そこの棺桶の蓋のうえで寝なければならなかった。」(国民文庫、「イギリスにおける労働者階級の状態2」、p242~243) こんなところに入って、生きながらえるだけなら、むしろ餓死したほうがましだと労働者が考えても不思議ではありません。
マルサスの「人口論」、「絶望の体系」
マルクスは「本源的蓄積」のなかで、過酷な「救貧院」がつくられたのはマルサス主義者のためだと述べています。マルサスの主書「人口論」は、エンゲルスの「国民経済学批判大綱」(1844年)のなかでも「かつて存在したもののなかでもっとも粗野で野蛮な体系であり、人間愛とか世界市民とかいったあの(国民経済学の*ykb)美辞麗句をすべて打ち倒した絶望の体系であった。」(ME、①、p544)、「プロレタリアートにたいするブルジョアジーの最もあからさまな宣戦布告は、マルサスの人口理論と、それから生まれた新救貧法である。」(国民文庫、「イギリスにおける労働者階級の状態2」、p236)と述べている通り、当時まだ合理主義・人道主義的なブルジョアにとどまっていたエンゲルスの目から見ても、恐ろしく無慈悲なものだったのです。では、マルサスの「人口論」の内容を見てみましょう。
マルサスは、はじめから自分の理論は悲観的で、「(ゴドウィンやコンドセルのユートピアへの*ykb)途上には大きな、しかもわたしの考えでは克服しえない困難があると思う。これらの困難を説明するのが、わたしの現在の目的である。」(河出書房、世界思想教養全集⑤「イギリスの近代経済思想史」、p176)と宣言します。そして、次の2つの公理を立てます。
①食料は人類の生存にとって必要である。
②両性間の情欲は必然的なものであり、だいたい現状のままでとどまるだろう。
以上の陳腐な「公理」の上に立ってマルサスは「人口の増加は人類の生活資料を生産する土地の力より不定限に大きい。人口は制限されない場合は幾何級数的に増加する。しかし、生活資料は算術級数的にしか増加しない。」とし、「この法則は、その全員が安楽に、幸福に、また比較的閑暇をもって生活することができ、自分や家族の生活資料の獲得について不安を感じないで暮らせるような社会が存在しうるという見解に対する決定的な反証となる。」(同、p179)と主張します。
その例証としてマルサスはアメリカ合衆国について「欧州のどの近代国家にくらべても生活資料がいっそう豊富で・・・早婚にたいする制限がいっそう少なくなたので、人口は25年間で2倍に増加した」(同、p181)と言います。そして、人口抑制のためには「窮乏や困難を予感すること」が必要と述べ、賃金の不足分を「救貧税」で補填する「スピーナムランド制」の撤廃を主張するのです。
次は多少なりとも経済学の匂いのする主張です。少し長いですが、全部引用しましょう。「労働者がその強い増殖力(まるでネズミ扱い!*ykb)で増えると生活資料が不足し、窮乏する。労働の価格も下落し、食料の価格は騰貴する。こうして労働者の生活と増殖は困難となり、人口増加は停滞する。一方、労働の低廉化は工作者(借地農場経営者*ykb)を奨励して耕作地の拡大と収穫量の拡大で食料と生活資料が増加する。こうしてまた、労働者の人口にたいする抑制が緩められるという具合で、こうした運動がくり返される。」(同、p184~185)
そしてこの自然な人口法則を阻害するのが、豊凶、戦争、疫病、救貧法、生産力の向上などだというのです。(同、p185) つまり、戦争や疫病は自然な人口増加をも抑制し、救貧法は自然な人口抑制を緩めるというのです。そして結論として「優勢な人口増加には、悪徳ないし窮乏を生み出すことなしに制限することができない」(同、p187) と主張します。その例として狩猟から農耕に入った北アメリカインディアンの人口急増や、ゲルマン民族の大移動、はては中国人はつつましく暮らしているから人口が多くても大丈夫だとか、偏見と独断の例証を連ねます。だから、「スピーナムランド制」は廃止し、働かないで生き残ろうとする労働者には、過酷な「救貧院」入りを強制する必要がある、現にイギリスでは実際の窮乏が人口の積極的制限として働いている(同、p195) というのです。
次に、マルサスの当時のイギリス救貧法(スピーナムランド制を含む)への憎悪の言葉を見てみましょう。「イングランドでは毎年貧民のために巨額の基金が集められているにもかかわらず、彼らの間には依然としてはなはだしい窮乏がみられるという事実は、しばしば話題になっており、つねに非常に驚くべきこととして語られている。」ここでマルサスが誰の立場にたっているか分かります。「寄付を増やし、貧民に対する給付を増やしても、市場における肉の量が増えるわけではない。肉の価格が騰貴するだけだ。・・・だから社会の最下層階級が18ペンス持っていようが5シリング(100ペンス*ykb)持っていようが、たいした相違はない。」「需要が生産を刺激し、供給が増えれば人口が増加し、(貧民の窮乏は*ykb)また同じになる。しかも、18ペンスにかわって5シリングを得た貧民は働かなくなるので生産が低下する。」「貨幣を与えると消費されるだけで生産されないだけでなく、他人の分け前を減らす。」(同、p198~p200)
マルサスはイングランドの救貧法は、貧民の窮乏を救済するために役立っていないだけでなく、次の点でかえって境遇を悪くするとまで言います。
①「養うべき食料を増やすことなく、人口を増加させること。
その結果、ますます多数のものが救済を求めるようになる」
②「貧民によって救貧院で消費される食料は、
本来もっと価値ある人々の分け前を減らしている。」
もう、たくさんです。マルサスの言い分はこれで終わりにしましょう。
マルクスは、マルサスの「人口論」への激しい敵意を抱きながら「いわゆる本源的蓄積」を書いたと思います。ところが、不破氏は、当時研究していた「恐慌論」の目で「資本論」全体を見ていたので、これまでykbdataが展開してた論の視点とはまったく違う解説と論及をしています。しかし、ykbdataは、ykbdataの視点こそ、マルクスの気持ちにぴったり沿ったものだと確信しています。実は「近代的植民理論」も「人口論」の一論点として取り上げられているのです。ここまで読んだみなさんは、あらためて、#017:資本の蓄積過程(その2)および#018:資本の蓄積過程(その3)、そして今回の「本源的蓄積」を読み直してみてください。そうすれば、マルクスの気持ちが分かると思います。
これで、第一部の研究を終わります。
2006年4月12日 ykbdata
|トップページ |第一部の目次 |前のページ |次のページ |メール|